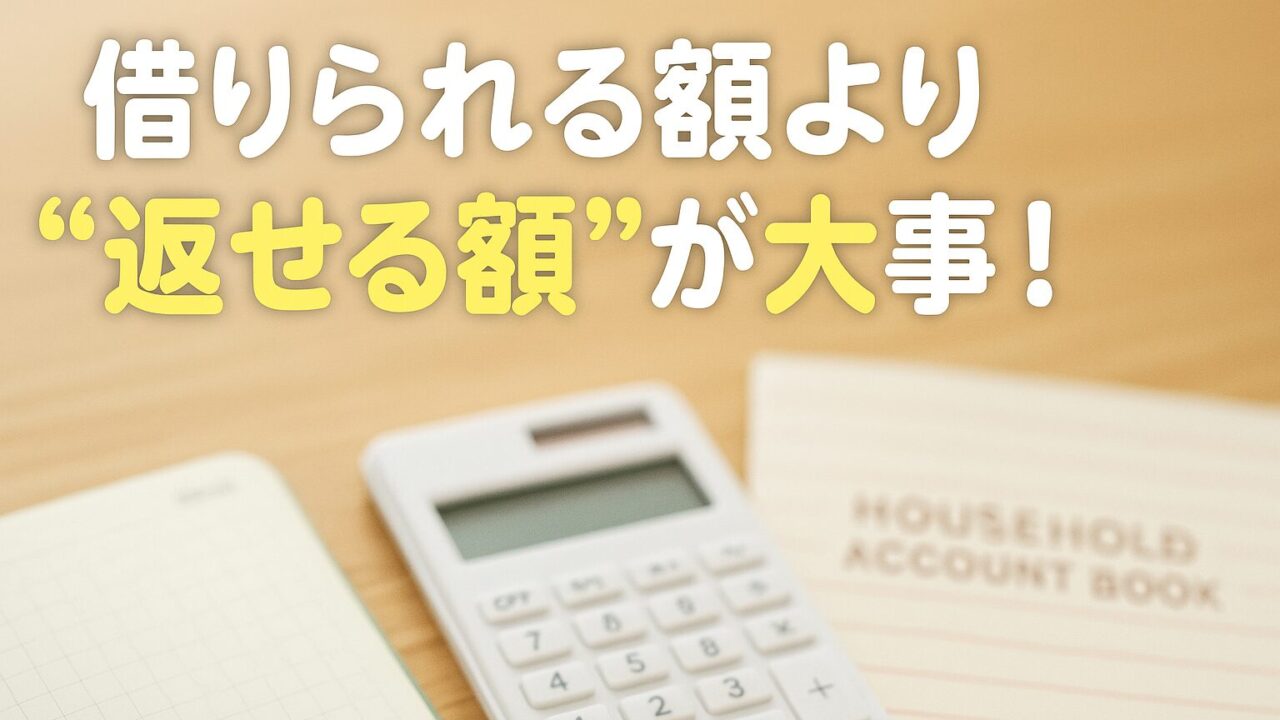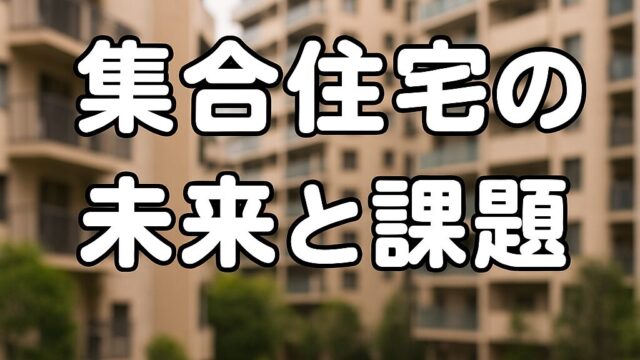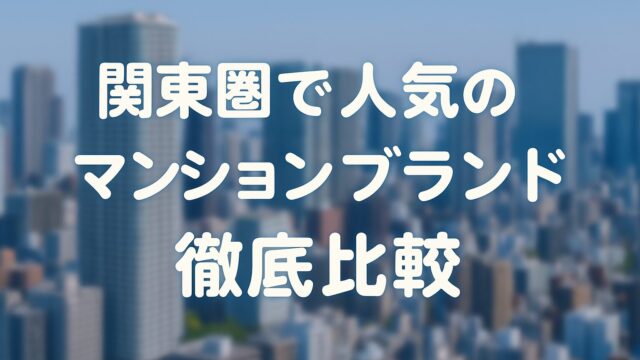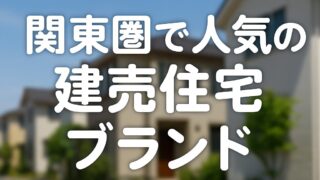はじめに:住宅ローンは「借りられる額」より「返せる額」
マイホームを購入するとき、まず気になるのが「自分はいくらまで住宅ローンを借りられるのか」という点ですよね。
住宅展示場や銀行のシミュレーションサイトでも、つい「年収から借入可能額をチェック」してしまいがちです。
しかし実際に重要なのは、銀行が「貸してくれる金額」ではなく、自分たちが「無理なく返せる金額」です。
ローンを組む時点では返せそうに見えても、子どもの教育費、車の買い替え、リフォーム費など、人生の支出は年々変わります。
「返せる金額」で考えないと、せっかくのマイホームが家計を圧迫する“重荷”になってしまうことも。
この記事では、共働き夫婦のケースを中心に、「返せる住宅ローンの考え方」や「実際にどのくらいの支出を見込んでおくべきか」をわかりやすく解説します。
住宅ローンの「借りられる金額」と「返せる金額」はまったく別物
銀行やフラット35などの金融機関は、審査時に「返済負担率(年収に対する返済割合)」をもとに貸付上限を決めます。
一般的には、年収の30〜35%程度が目安とされています。
たとえば、夫婦の合算年収が800万円の場合、単純計算で約2,800万円〜3,200万円程度の借入が可能とされます。
しかしこれは“借りられる上限額”であって、“返していける安心ライン”ではありません。
実際に家計を考えると、次のような支出が重なっていきます。
- 固定資産税・都市計画税などの年間税負担
- 火災保険・地震保険などの維持費
- マイカーの維持費(駐車場代・保険・ガソリンなど)
- 子どもの教育費(幼稚園〜大学までで数百万円〜1,000万円超)
- 家の修繕・リフォーム費(10〜20年後に数百万円規模)
こうした支出を考慮せずに「上限いっぱい借りる」と、日々の生活がカツカツになるリスクが高まります。
共働き夫婦の「収入合算」で借りるときの注意点
共働き世帯が増えた今、夫婦の年収を合算してローンを組むケースも一般的になっています。
たとえば、夫年収500万円+妻年収300万円=合算800万円でローン審査を受けると、借入可能額は一気に増えます。
しかし、ここで忘れてはいけないのが「夫婦どちらかの収入が減る可能性」です。
出産や育休、転職、病気などで一時的に収入が減ると、返済計画は一気に苦しくなります。
つまり、夫婦二馬力を前提にフルに借りるのは危険。
返済シミュレーションを立てるときは、次のように考えるのが現実的です。
- 夫の収入だけで最低限の返済ができるか?
- 妻の収入は“貯蓄・教育費・ゆとり費”として余力に回せるか?
住宅ローンを「夫婦二人でがんばって返すもの」と考えるより、「どちらか一方でも返せる設計」にしておくと安心です。
理想的な返済負担率の目安は?
住宅金融支援機構などでは「返済負担率35%以内」が基準とされていますが、実際の生活を考えるとやや高めです。
教育費や老後資金を同時に貯めていくことを考えると、理想は25%前後に抑えるのが現実的です。
たとえば、年収700万円の家庭なら:
- 借入額3,000万円・金利1%・35年ローン → 毎月約8.5万円の返済
- 返済負担率 約14.6% → 余裕あり
- 借入額4,500万円・金利1%・35年ローン → 毎月約12.7万円の返済
- 返済負担率 約21.8% → ギリギリ現実的
- 借入額5,500万円・金利1%・35年ローン → 毎月約15.5万円の返済
- 返済負担率 約26.5% → 教育費期に入るときつい
「借りられる額」よりも、「生活費・貯蓄・娯楽も確保しながら返せる額」を重視しましょう。
“カツカツ返済”は本末転倒。生活のゆとりもコストに含めて
家を買うとき、多くの人が「家賃並みで返せるなら大丈夫」と考えます。
しかし、マイホームの維持費は賃貸のときよりも多くかかります。
さらに、ローン返済が家計の大部分を占めると、旅行や外食などの“心のゆとり費”が削られがちです。
家を買っても生活が苦しくなれば本末転倒です。
理想は、「月々の返済+固定費+生活費」を支払っても、月に3〜5万円程度の“ゆとり”が残るライン。
これがあると、予期せぬ支出(冠婚葬祭・家電の故障など)にも柔軟に対応できます。
忘れがちな「修繕・メンテナンス費」も確保を
新築でも、10年、20年と住めば必ず修繕費が発生します。
外壁塗装や屋根補修、給湯器・エアコンなどの交換……トータルで数百万円にのぼることも珍しくありません。
たとえば、戸建てなら10年ごとに以下のようなメンテナンスが必要です。
- 外壁・屋根塗装:100〜200万円
- 給湯器・トイレ交換:20〜40万円
- エアコン入替:数十万円
- シロアリ防除・防水工事:10〜30万円
月々のローン返済だけで精一杯だと、こうした修繕費を積み立てる余裕がなくなります。
住宅ローンを組む段階で、毎月1万円でも「修繕積立」に回す意識を持ちましょう。
「35年ローン」でも繰上返済を想定しておこう
ローン期間を長めに設定して月々の負担を軽くし、余裕があるときに繰上返済するのが賢いやり方です。
最初から短期間ローンにすると、月の返済が高くなり家計が圧迫されがち。
たとえば、35年ローンで組んでおき、10年目や15年目にボーナスや貯金から繰上返済を行えば、利息負担を大幅に減らせます。
「長く借りて早く返す」戦略は、今の時代の金利環境にも合っています。
シミュレーションで“リアルな家計”を見える化
住宅ローンは金額が大きい分、感覚的に決めてしまうと危険です。
返済額だけでなく、固定費や生活費、子どもの将来費用を具体的に見える化してみましょう。
たとえば:
- 住宅ローン:毎月10万円
- 固定費(光熱費・通信・保険):5万円
- 食費:6万円
- 教育費:3万円
- 生活費その他:4万円
- 修繕積立:1万円
- 合計:月29万円
共働きで手取り40万円なら、貯金やゆとり費に毎月10万円程度残るため、安心ライン。
手取り35万円であれば、少し厳しめですがやりくり可能です。
このように、「ローン返済が家計の1/3以内」を目安に設定すると、無理なく暮らせる可能性が高くなります。
マイホーム購入は“長期戦”。焦らず冷静に
「いまが買い時」と言われると焦ってしまうものですが、住宅ローンは30年以上の長期契約。
一時的な収入やボーナスをあてにして決めると、のちのち苦しくなるリスクがあります。
特に、共働きの夫婦ではライフステージの変化が多く、収入・支出のバランスが変わりやすいもの。
子育て・転職・親の介護など、人生のイベントを長期的に見据えた上で計画を立てましょう。
まとめ:「借りられる額」より「返せる額」で幸せなマイホームを
住宅ローンは一度組むと長い付き合いになります。
借入可能額の上限に惑わされず、実際に自分たちの生活が続けられるかを基準に判断することが何より大切です。
共働き世帯なら「片方の収入だけでも返せる範囲」で組み、修繕費や教育費も含めた長期的な家計設計を。
そして、「マイホームを買っても家族の笑顔が続く暮らし」を実現することが本当のゴールです。
マイホームは人生の幸せを支える“器”です。
無理のない返済計画で、心にも家計にも余裕のある暮らしを育てていきましょう。